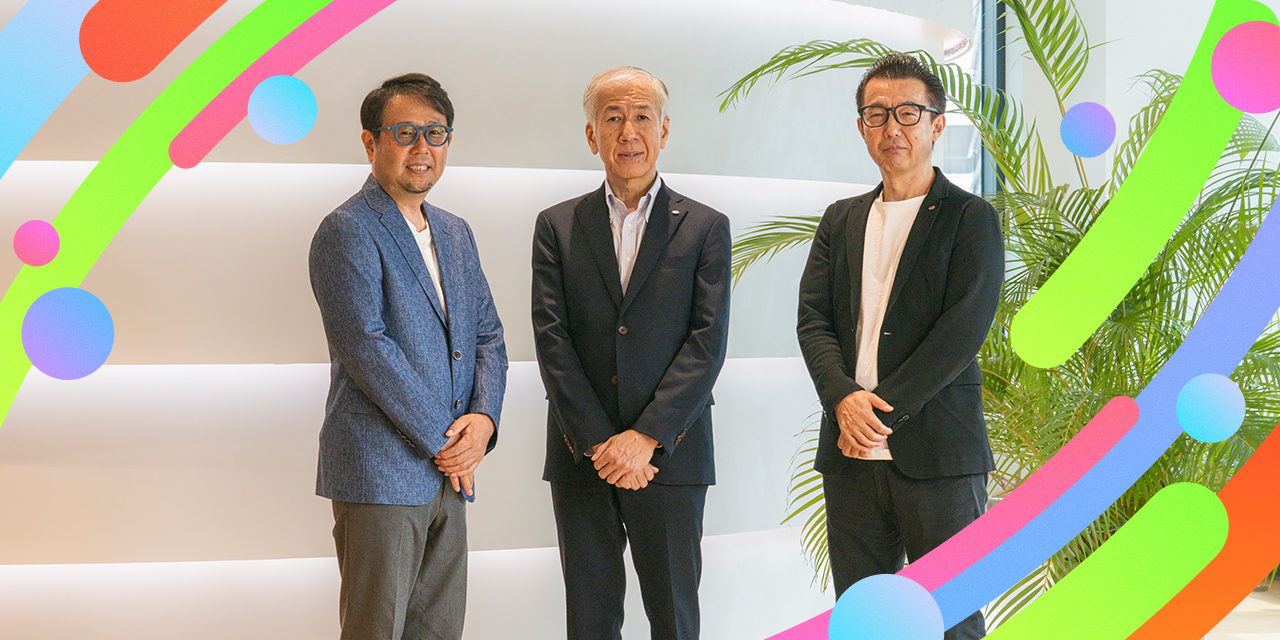
HISサステナビリティウィーク2025 心躍る未来を目指してオープニング対談「HISのサステナビリティ経営について」
2025年9月22日から10月5日まで、HISの社内イベントとして「HISサステナビリティウィーク2025」が開催されました。HIS社員が「心踊る」未来を目指して、持続可能な社会の実現を目指す取り組みについて理解を深められるよう、HISが取り組むサステナビリティ事例紹介、ワークショップ、オンラインセミナーなどが実施されました。
イベントのオープニングを飾った、特別対談の模様をお届けします。駒沢女子大学 鮫島教授がファシリテーターとなり、HIS代表取締役社長 矢田、取締役 山野邊と、HISのサステナビリティ経営の意義、地域との共存・共栄、そしてアウトバウンド再興などをテーマとし、多角的な視点から議論を交わしました。

駒沢女子大学 観光文化学部 教授 鮫島 卓
HISにて経営企画、海外旅行・国内旅行のツアー企画や新規事業を推進し、2015年スタディツアーの取り組みで観光庁長官賞を受賞。その後、JICAの専門家として国際協力や観光開発に従事。現在は駒沢女子大学観光文化学部教授として教鞭を執る傍ら、観光地の産業集積とイノベーションに関する研究に取り組む。
近著『旅行業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書』
https://www.komajo.ac.jp/uni/faculty/d_tourism/index.html

株式会社エイチ・アイ・エス
代表取締役社長 CEO 矢田 素史

株式会社エイチ・アイ・エス
取締役 HIS JAPANプレジデント 山野邊 淳
HISのサステナビリティ経営の意義
鮫島:私がHISに入社した当時の1996年から社員も増え、社会的な見方も変化していると感じています。HISが社会に影響を与える側になり、自社の利益だけでなく、社会や地球規模の課題に取り組むことは非常に理にかなっていると思います。HISのサステナビリティ経営を進める上で、矢田社長が考えていること、問題意識、ゴールについて教えていただけますでしょうか。
矢田:HISはマテリアリティとして、重要課題を7つ挙げており、そのうち3つがサステナビリティに直結しています。
1つ目は「多様な人材の活躍」です。労働人口が減少する中で、HISは従業員一人ひとりが活躍でき、優秀な人材に選ばれる企業にならなければなりません。特に女性従業員の比率は高いものの、管理職比率は20%を切っている現状があります。社員が働きがいを感じ、心躍る仕事ができる企業を目指し、2026年までに働きがい係数を80%に、女性役員・管理職比率を20%にすることを目標としています。今年からは「HIS Group Award」という表彰制度を新設し、営業成績の表彰だけでなく、HISのPurpose"「心躍る」を解き放つ"に繋がる業務に関するエピソードを募集し、全スタッフの投票制で受賞者を決めるPurpose部門も設けています。
2つ目は「地球環境の保全」です。観光産業が排出するCO2は全産業の8%を占めており、いつまでも旅を楽しめる地球環境を維持していくことを目指しています。2026年までにプラスチック製品使用量とコピー用紙使用量をそれぞれ2019年対比で70%削減し、2030年までに自社CO2排出量を実質ゼロにすることを目標としています。取り組み事例としては、HISハワイ法人が実施しているジョギングとゴミ拾いを組み合わせた「プロギング」活動やアラワイ運河での水質改善運動、HISグループのラグーナテンボスで実施している海洋プラスチックごみ問題ワークショップなど、世界各地で様々な活動を行っています。

3つ目は「地域社会との共生」です。お客様だけでなく、地域社会からも選ばれる存在となることを目指しています。具体的な数値目標はありませんが、人権方針に則り、地域社会の人権を尊重し相互理解を促進することが重要と考えており、オーバーツーリズム対策も推進していきます。「マラマハワイ※1」、スタディツアー、ユニバーサルツーリズムなどの取り組みは、JATA主催のSDGsアワードも受賞し、社内外から高く評価されています。また、地域創生のための専門部署を設置し、自治体、NPO、NGOとの連携を強化しています。
地域共存・共栄の取り組み
鮫島:次に、地域との共存共栄についてお聞きしたいのですが、観光学では旅行業は観光産業の一部であり、旅行者と観光事業者を仲介する役割とされています。しかし、仲介で終わってしまうと、季節変動による顧客の偏りや閑散期対策、非正規雇用の問題など、課題が生じることがあります。長期的な関係構築と地域との共存共栄は、サステナビリティの観点から非常に重要です。HISでの取り組みや今後やっていきたいことを教えてください。
山野邉:地域の方々とお会いする機会が多いのですが、まず最初に話すようにしているのが「互いに利益を取るものにしないと活動は継続できない」ということです。地域のために活動したいという熱意がある一方で、HISのような民間企業が継続して地域と共に活動を続けていくためには、HIS・地域双方に利益が残るような事業の仕組みづくりをしていかないといけないと思っています。
「マラマハワイ」の取り組みでは、ハワイ州観光局のパートナーとして、現地環境に配慮した観光を強化しています。旅行者の方々がこうした活動に参加することに喜びを感じていただいている様子を目の当たりにし、このような取り組みを組み込むことの重要性を感じています。

また、最近では地域活性化に取り組む株式会社さとゆめに出資しました。彼らは地域に入り込み、地域が抱える問題点を掘り起こし、解決策を提供している企業です。彼らを支援し、共に地域と伴走することで、より良い課題解決の提案ができるのではないかと考えています。
HISは海外への支店展開を通じてサウジアラビアなど新たなデスティネーション開発も行っています。これはオーバーツーリズム対策のための観光客の分散や、お客様に新たな旅先の魅力の提案にも繋がると考えています。
鮫島:矢田さんは九州産交グループでの長い経験がありますね。地域に入ってきた頃と、HISの社長として異なる立場から、地域との共存共栄をどのように理解されていますか?
矢田:私は2005年から2021年までの15年間、熊本で九州産交という会社の経営に携わりました。当時、経営が行き詰まっていた九州産交をHISグループと地元企業連合が支援することになり、地元には期待と不安が渦巻いていました。私たちは「ちゃんとしっかり腰を下ろして、事業拡大と地域のためにやっていく」と宣言し、地元に根付いた様々なプロジェクトを実施しました。
その中で、地元における基幹施設であった古いバスターミナルの再開発は、HISが本気であるという理解が広がり、地域に根を張ることができたと思っています。2016年の熊本地震の際、再開発の途中で行政から一時中止を求められましたが、地元経済団体からの強い後押しもあり、継続することができました。結果として、熊本地震からの復興のシンボルとまで言っていただけました。九州産交はHISグループの代表として、地域に根を下ろさせていただいていると感じています。
鮫島:地域との関係構築は時間も掛かり、信用を得るのは大変ですよね。ただ言われたことを受けるのではなく、話し合って共に作り上げる提案型の関係が長く続くことが重要に感じます。WIN-WINの関係を築くことが重要だと改めて思います。

観光におけるマナーの問題や文化摩擦の解消

鮫島:次に、観光におけるマナーや文化摩擦の問題についてお聞きします。良かれと思って行った行動が、社会常識の違いから摩擦を生むことがあります。昔は「旅の恥はかき捨て」と言われる時代もありましたが、それでは地域に迷惑をかけてしまいます。最近、「ツーリストシップ」という言葉が生まれています。これは旅行者が観光地域に喜ばれる存在となるためのもので、旅行先への配慮や貢献を目的とした、スポーツマンシップの旅行者版と言えるでしょう。このツーリストシップについて、率直にどのようにお考えでしょうか?
山野邉:ゴミ拾いのような地域の環境に貢献する体験は、旅行者自身も喜び、旅の楽しみ方の一つになると思います。これを旅行者自身が考えるきっかけになる言葉になるのではないでしょうか。HISハワイ法人が実施している「プロギング」活動は、団体旅行でも行程に組み入れています。単に送客するだけでなく、お客様へ旅行先に貢献し、その土地に行く意義を考えていただくという新たな提案をしています。このような取り組みを通じて、HISがお客様と一緒に、「ツーリストシップ」の意識を広めていきたいと考えています。
鮫島:旅行会社はこれまでお客様の要望に応えるのが役割でしたが、観光地のことを考えると、良い旅行者を育てるという新しい局面に差し掛かっていると感じています。
アウトバウンドの再興に向けて
鮫島:続いて、HISが海外旅行をメインに成長してきた会社として、そのDNAを活かしつつ、旅行者に提供するだけでなく旅行者を育てることも必要ではないかと考えています。持続可能な経営のためには、海外旅行の低迷を何とかしなければなりません。これは業界全体の共通認識だと思います。
日本の出国率は世界的に見ても非常に低く、特に20代女性の出国率が最も高い一方で、20代男性の低さが大きな課題です。また、地方の出国率も都市部に比べて低いという構造的な問題もコロナ前から変わっていません。こうした中で、HISがアウトバウンド再興に向けてどのような取り組みをされるのかお聞きしたいです。
山野邉:アウトバウンドの再興は、私自身が本当に強く手掛けていきたいと思っているポイントです。単純に言えば、海外旅行の意義、価値、魅力をしっかり伝えていくことだと考えています。パスポート保有率の低さや為替、海外情勢などを理由にしないことが重要です。行きたい、行く意義がある、楽しさがある、何か新しいものが生まれる、そういったことがあれば、おのずとパスポートを取り、海外に出ていくと思います。かつては海外に出ること自体が憧れだった時代にHISは成長しましたが、今後は「海外で何ができるか」、「現地への貢献」といった具体的な目的や意義を伝えることが重要です。ネットで情報が得られる時代だからこそ、生で体験することの意味や、現地に行ったからこそ解決できること、現地を助けられるような貢献をしたいという気持ちが強い世代に、その価値をしっかり伝えきれていないと感じています。
HISはかつて旅を大衆化させた一助となりましたが、今度はその流れを大きく変え、行くことに目的や意義をお客様にしっかり伝えることで、旅行会社だからこそできる体験を提供していきたいです。とにかく海外に出ることの素晴らしさを伝えていきたいと思っています。
鮫島:日本の観光はインバウンドが主流に見えますが、実はインバウンドビジネスを成功させるためにはアウトバウンドの経験と知識が重要だというロジックをどう再構築するかが重要ではないでしょうか。今、インバウンドに取り組んでいる地域では、海外経験豊富な人がガイドや宿を経営していますが、アウトバウンドとインバウンドを切り離さずに、アウトバウンドの重要性を抱えながらインバウンドを進めるという考え方についてどう思われますか?
矢田:ツーリストシップにも通じる異文化交流や双方向交流の思想に非常に共感しました。鮫島さんのお話にあったように、インバウンドに取り組むには海外を知らなければならないという話は、逆もまた真だと思います。今、訪日のお客様と接することにより、世界に対する目を開いたり、興味関心を抱いたりする機会が増えています。私も街を歩いていると、外国の方に道を尋ねられたり、美味しいラーメン屋を聞かれたりすることがありますが、そうした交流を通じて、海外への興味関心が生まれることもあります。
今年は訪日観光客数が3,000万人を超える見込みですが、この機会を活かして国民の国際性を高めていくことに関して、HISとしても何かできるのではないかと感じています。
山野邉:ツーウェイチャーター※2の実施など、それぞれの地域の人々の交流に繋がっていくような、中長期的な継続が重要だと考えています。
鮫島:はい。ぜひHISでも頑張っていただきたいなと思います。

※1 マラマハワイ・・・ハワイ語で「ハワイを思いやる心」を意味します。HISは、ハワイ州観光局日本支局と自然環境、伝統・文化を守り、地域と観光客が共に持続的な社会を作り上げていく「リジェネラティブ・ツーリズム(再生型観光)」を促進すべく、「マラマハワイ」の推進に向けたパートナーシップ協力覚書を締結しております。
※2 ツーウェイチャーター・・・フライトの区間を往復して双方から送客する方式。
